こんばんわ。ゆうゆあぱぱです。
今日はウーパールーパーの『ぷかぷか病』について体験を交えて書いていきます。
我が家のウパとクロが水面付近でぷかぷか浮いていることが多くなりました。3日前くらいからです。


普段から空気を吸いに水面に上がってきたり、ぷかぷか浮く事を楽しむ事はあります。ただ、浮かび続けている場合は、ぷかぷか病の可能性があるので注意が必要です。
それでは、ぷかぷか病の原因と対策についてお伝えしたいと思います。
ぷかぷか病とは
ぷかぷか病は、ウーパールーパーなどの両生類に起きる症状です。本来ウーパールーパーは水底で生活する生き物ですが、病気になると体を沈める事ができなくなり、水面に浮いたままになります。体を沈めようともがく事で体力を消費してしまいます。重症化すると仰向けにひっくり返り、餌を食べられず命を落とす事もあるそうです。ただし、早期に発見し対策を行えば、治すことができる病気です。
ウーパールーパーが浮く原因
ウーパールーパーが浮かぶ原因は、水面で取り込んだ「空気の浮力で浮く」場合と、お腹にガスが溜まり、「ガスの浮力で浮く」場合があります。気をつけなければいけないのはガスの浮力で浮く場合です。
ガスが貯まる原因
消化不良
食べすぎや便秘で餌が排出されない場合、腸内で発酵してガスが溜まります。特に人工飼料を食べたときに発生しやすいです。
水質悪化
糞や食べ残しからアンモニアや亜硝酸が蓄積されると、腸内環境が乱れてガスが発生しやすくなります。また水の濁りやpH変化も起こり、消化不良が起こりやすい環境になっていきます。
水温の急変
変温動物のウーパールーパーは急な温度変化に弱く、代謝や消化機能が乱れます。特に夏場の高水温は腸内トラブルのリスクが高まります。
感染症
細菌や寄生虫などにより内臓や消化管がダメージを受けると、消化不良やガスの発生に繋がります。
上記のような原因がありますが、主にエサの消化不良が原因とされています。人工飼料は特に注意が必要です。
ぷかぷか病の対処と治療法
ぷかぷか病の治療では、消化不良を改善しガスを排出することが大切です。
消化不良を治すための対策
- エサを一時中断する。または給餌量を減らす。
- 生餌に切り替える。
- 水温を一定に保つ。
- 水換えで水質を改善する。
等が挙げられます。
どれも毎日の世話に一工夫すればできそうですね。
我が家での対応
我が家では、給餌量の調整と、こまめな水替えを中心に対応しています。まず水槽の半分ほどを水換えします。そして1日餌を抜きます。改善が見られない時は、餌を冷凍赤虫に切り替えたり、2日に1回の頻度で水槽の1/3ほど水換えをします。急な水質変化はウーパールーパーの負担になります。私は1回の水換え量を減らしたり、できるだけ水温を合わせるように注意しています。
糞が出ると治ることが多いです。
また、頻繁に浮かぶ時は人工試料が古くないか確認します。古い人工試料はガスが溜まる原因になるので買い替えをお勧めします。
ぷかぷか病は早期発見と早期対策が大切
ぷかぷか病は重症化すると命を落とす事もあるため、早期発見と早期対策が大切です。早期であればウーパールーパーの消耗が少なく、回復も早くなります。また、対策も給餌や水替えの工夫など、普段の世話の見直し程度で済むため、飼い主の負担も少ないでしょう。
病気ではないこともある!備えたら心配しすぎず見守ろう
ぷかぷか病についてお伝えしましたが、浮かんでいるからと言って必ずしも病気ではありません。ウーパールーパーは水面で空気を吸い込みすぎてうっかり浮かんだり、自分から浮かぶ事を楽しんでいるだけの事もあります。水底に戻れる様子が見られるなら大きな問題はないでしょう。大切なのは「万が一の備え」はしておきながら、必要以上に不安にならず見守る事だと思います。
まとめ
- ぷかぷか病は主に消化不良が原因
- 水質管理・給餌の工夫で予防できる
- 早めに対処すれば回復可能
- 備えたら心配しすぎず見守る事が大切
今回は水質改善のため、水替えと外部フィルターの清掃をしました。念のため明日まで餌を控える予定です。ウパもクロも水底で過ごす様子が見られました。ぷかぷか病ではなさそうです。

それにしても、ぷかぷか浮かびながら、何を考えているんでしょうね。
本当に面白いなと思います。
・・・明日もいいことがありますように

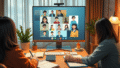

コメント